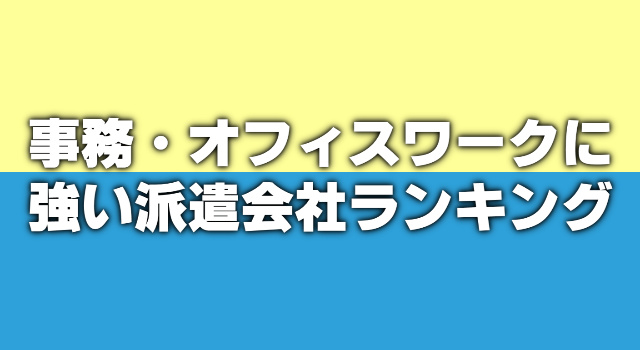
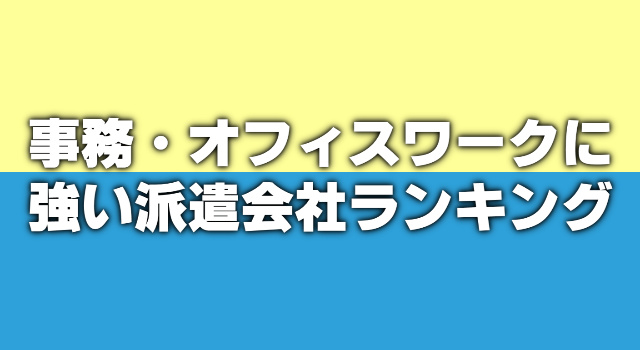

理系出身者であれば、研究職に憧れを持つ人も多いと思います。
しかしながら、研究職は新卒の就職活動で内定を勝ち取るのはかなり倍率が高く、優良企業から内定をいただくのは至難の業。
ですが、正社員ではなくても、派遣なら未経験から就業できる案件や、ブランクがあってもできる求人が用意されているなど、研究者として大手・優良企業で働くチャンスがあります。
この記事では研究職に就きたい方向けに、「研究職の派遣って実際どうなの!?」という根幹部分について、実際に研究職の派遣を経験した立場から、その業務内容、給与面、メリット・デメリット、正社員型派遣、将来性などについて紹介させて頂きます。
条件が悪くないならこれから応募を検討したいと思っているなら、この記事を参考に検討してください。
目次

遺伝子工学
遺伝子治療を目的とした前臨床試験、次世代シーケンサーを用いたcDNAライブラリの構築業務 など
タンパク質工学
インフルエンザワクチンの開発、バイオマスエネルギーに用いる酵素探索および精製業務など
in vivo、 in vitro試験
幹細胞を用いた皮膚・角膜などの再生医療研究、各種がん研究、神経科学研究 など
微生物
バイオマス向けの酵素や微生物のスクリーニング、重金属排水浄化の微生物試験など
有機合成
原薬候補物質の探索研究、有機EL素子となる有機化合物の合成業務など
分析化学
フィルム開発における表面分析、残留農薬の微量分析、HPLCを用いた医薬品分析など
半導体プロセス
電子顕微鏡を用いた有機絶縁膜の表面分析業務、MEMSデバイス/ICデバイスの評価業務 など
セラミックス
高温断熱材に使用されるセラミックスファイバーの開発業務、セラミックスとプラスチックの複合材料開発など
高分子化学
自動車部品における新規樹脂材料の開発、人工血管や歯科材料などの生体高分子材料の研究開発など
製薬メーカー
医薬品の品質管理(HPLC等)、再生医療の研究(細胞培養)、医薬品開発(有機合成)など
食品メーカー
製菓の試作・官能検査、飲料の衛生検査、新製品開発に伴う品質試験(HPLC、GC等)など
化学・材料メーカー
ガラス・樹脂・セラミックス・ペンのインク開発(有機合成、SEM、FT-IR、引張り試験等)など
化粧品メーカー
基礎研究(遺伝子、タンパク質、細胞培養)、原料の成分分析(HPLC等)など
公的機関
基礎研究、新治療法開発の為の分子生物学実験(細胞培養、遺伝子解析)など
派遣研究者だと、「関われる仕事の範囲が限られるのではないか?(やりがいがなさそう)」と思われる方もいますが、これは『派遣先企業による』というのがわたしの答えです。
例えば、派遣先企業がルーティンワーカーのポジションで派遣社員を募集しているのであれば、派遣先の指揮命令を着実に熟すだけの業務になってしまいます。
この場合、責任は軽く時間拘束もほとんどないので、プライベートを優先している人にはいいかもしれませんが、その分給与も安いケースがほとんどです。
一方、派遣先社員と同等のパフォーマンスや能力を求めている派遣先企業もあります。
そのような派遣先の場合、業務内容にほとんど差がなく、それなりのプレッシャーものしかかってきますが、その分給与も高く、やりがいのある仕事になってくるでしょう。

派遣社員は外部の人であるため、「特許や機密事項に関わる情報に関してオープンにされない、出張や発注の権限などは与えられない、共有サーバーにアクセスできない」など、不都合なことを抱えながら業務をしなければならないこともあります。
あくまで派遣先によりますが、このようなことも想定しておきましょう。
一般登録派遣
月収:24万~32万円(時給相場:1500~2000円)+残業手当
※1日の労働時間8時間、1カ月の勤務日数:20日と想定。
年収:288~384万円+残業代
正社員型派遣
月収:21万~30万円+住宅手当+扶養手当+残業手当+通勤手当
年収:350~500万円+残業代
※月収+賞与(年俸制の場合、賞与の支給なし)

特定派遣は派遣先が派遣会社に支払う金額が高いこともあり、特定派遣の収入面は一般登録派遣と比べ高いのが一般的です。
また、福利厚生に関しても、住宅手当・通勤手当などが支給されるため、特定派遣の方が充実していると言えます。
メリット
実務経験者や新卒でなくても、未経験からでも研究職に就けることが派遣で働く1番のメリットでしょう。
研究職は枠が少ないうえ、高倍率の選考試験をくぐり抜けて、やっと就ける職種です。
派遣であれば、その厳しい選考をスキップして研究職のキャリアを積むことができます。
また、派遣先に優秀な研究員がいた場合、大きな刺激となり、能力の向上やモチベーションの維持にも繋がります。
さらに、派遣契約は派遣先会社と派遣会社の契約で働くことになるため、理不尽なハラスメントが起きにくいこともメリットと言えるでしょう。
デメリット
派遣先の正社員と比べると、給与・昇給がそれほど期待できないことが1番のデメリットです。
派遣先でキャリアを積むことはできますが、正直な話、当たり外れがあります。
また、自分の能力を高めていく際、研究や実験の経験しか積めないことが年齢を重ねるにつれて障壁になっていきます。
とくに業者・共同研究先などの外部とのやり取りは派遣先の社員が行うため、携わることができません。
将来的なことを考えると、3~5年程度派遣でキャリアを積んだら、メーカーへの就職を考えた方がいいかもしれません。
| 正社員型派遣 | 一般登録派遣 | |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 派遣社員 |
| 給与形態 | 月給制(固定給あり) | 時給 |
| 賞与 | 〇支給される (年俸制は支給されない) |
✕支給されない |
| 住宅手当 | 〇支給される | ✕支給されない |
| 通勤手当 | 〇支給される | △案件による |
| 引っ越し費用 | 〇支給される | ✕支給されない |
| 退職金 | △会社によって支給される | ✕支給されない |
| 賃貸入居費用 | 〇支給される | ✕支給されない |
| 派遣先 | △派遣会社が指定 | 〇派遣社員が選択 |
| 派遣先が承諾後の拒否 | △不可(中途採用で入社前であれば可能な場合もある) | 〇可 |
| 無就業期間中の給与 | 〇一部支給される | ✕支給されない |
| 無就業期間中の業務 | あり(ない場合もある) | なし |
両者を比較すると、明らかに正社員型派遣の方が、一般登録派遣より待遇面・安定性が高いと言えます。
とくに一人暮らしをする人にとって、住宅手当や引っ越し費用の支給は大きなメリットだと考えていいでしょう。
しかし、派遣会社の正社員であるという立場から、派遣社員が派遣先を選択できない(場合によっては希望しない派遣先で働かなければならない)というデメリットがあります。
待遇面や安定性より、フレキシブルな働き方を重視している人(女性で子育てをしながら派遣で収入を得たい人や掛け持ちで仕事をしている人など)は、一般登録派遣での就業が向いていると言えます。
良し悪しに関しては、結論派遣先に依存します。
例えば、正社員にステップアップできる派遣先であれば、かなり恵まれた環境だと思います。
また、正社員になれないにしても「派遣先の研究員と同レベルの仕事に携わることができる」、もしくは「ニーズのあるスキルアップができる」ならば、転職活動をする際にも大きなアピールになります。
わたしの知人は、大手製薬会社の子会社に配属されて正社員になった人や、派遣先での業務経験を活かし、別の製薬会社に転職を決めた人もいます。
正社員型派遣(特定派遣)の研究職は、就職してからが勝負になります。
自分の能力を高めるだけでなく、転職先を決める意志力や忍耐力が重要になってきます。
また、特定派遣で働く場合、どうしても研究に特化した経験を積むことになります。
なので、名刺交換や電話応対などの基本的なビジネスマナーができていない特定派遣社員も少なくありません。
こうならないためにも、研究や実験業務以外のことにも積極的に勉強する必要があると言えるでしょう。

研究職の人材派遣は、正社員型派遣(特定派遣)が主流なので、正社員の面接とそれほど大きく違いはありません。
ただ、採用ハードルは正社員採用試験のように高くはないので、そこまで心配せずに応募を検討してください。
 理系出身であれば、簡単に研究職の派遣に転職することができます。
理系出身であれば、簡単に研究職の派遣に転職することができます。
というのも、どの企業も研究開発を進めていくにあたり、人材が不足しています。
ですが、だからと言って正社員を採用すれば、大きな人件費がかかるため、派遣社員で人材を補おうとするのです。
プロジェクトの進み具合で契約を延長or満期修了もできるので、派遣先からすれば、ローリスクでの人材確保と言えます。
さらに、精通している専門用語を理解しているため、配属後もある程度教育をスキップして戦力にすることが可能です。
また、未経験の分野であっても、理系出身者であれば、問題なく業務をこなせるという期待もあるでしょう。
文系出身の場合、派遣社員として就業できないかというとそうでもありません。
派遣会社によっては、スキルアップ研修(基礎化学の座学、HPLC分析、有機合成、遺伝子操作、細胞培養)などのカリキュラムを用意して、文系出身者でも就業に困らない配慮をしてくれる派遣会社もあります。
ですが、就業先の業務においてはルーティン的な仕事に限定されるかもしれません。
 「派遣社員であれば、複数の研究機関で研究のキャリアを積みやすい」
「派遣社員であれば、複数の研究機関で研究のキャリアを積みやすい」
「別に目標を持っている(公務員試験や弁理士試験合格など)」
「理系の知識やスキルを活かしつつ、とりあえず働けるから」
など、新卒で研究職の派遣として働く理由は、人によって異なります。
ですが、実のところ「メーカーでの研究職を希望していたけど内定をもらえなかった。だけどどうしても研究職に就きたいため、研究職の派遣を選んだ」という人が大部分だと思います。
新卒で働くことは何ら問題ありませんが、何事も目的を持ったうえで、研究職の派遣を選ぶことが大切です。
研究職の正社員型派遣(特定派遣)の将来性に不安を感じている人も多いと思います。
「研究職で働く派遣社員に将来性はあるのか?」「このまま続けて良いものか?」の回答としては、その人の能力や専門性次第という部分が大きいかと思います。
能力が高く、派遣先のニーズに合った専門性を持っているのであれば、40代、50代になっても需要があるので生き残れます。
ですが、年齢を重ねるにつれて派遣先が限定されていくのは事実です。
実際のところ、派遣社員が「人材派遣という働き方に不安を感じている」ことを派遣会社は知っています。
そのため、派遣会社によっては、派遣会社の運営側(営業職、キャリアコーディネーターなど)のポストや、派遣会社が設立した研究所で派遣先からの受託業務に携われるポストに就かせるなどのキャリアパスを用意してくれる派遣元も一部あります。
もし、特定派遣を続けていくうえで将来的に不安を感じているのであれば、現状に甘えず、「派遣会社に交渉して運営側に就かせてもらう、自分で転職先を見つける、派遣先で実績を残して自分を売り込んで転籍を狙う、自分でビジネスを立ち上げる」などして、自分で道を切り開いていく必要があります。
こんな人にオススメ
派遣で研究職のキャリアを積む場合、色々と不安があると思います。
ですが、「どうしても研究がしたい、まずは色々な研究機関で仕事をして経験を積みたい、大学院時代の専門を活かした仕事に就きたい」という人には研究職の派遣はとてもおすすめです。
中には、自営をされていて別に収入源があるにもかかわらず、実験が好きだという理由だけで研究職の派遣をされている人がいました。
なので、副業的な位置づけで研究職の派遣をするのもいい働き方かもしれません。
研究がしたい人にとって、未経験でも研究のキャリアを積めることは大きなメリットですが、将来的な給与面や安定性が不透明であることがデメリットです。
もし、それでも研究職に就きたいのであれば、待遇面や安定性からして『正社員型派遣』がいいと思います。
正社員型派遣で研究職に就いてからも、給与アップを図りたいのであれば、メーカーへ転職せざるを得ません。
研究職の派遣に就こうか迷っている方は、こちらの記事を参考にして頂ければ幸いです。
研究・開発における人材派遣の主な分野(どんなお仕事があるのか?)
派遣先のメーカー(どんな就業先になるのか?)
について紹介します