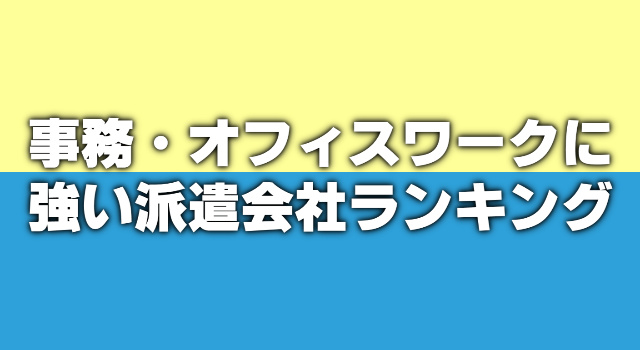
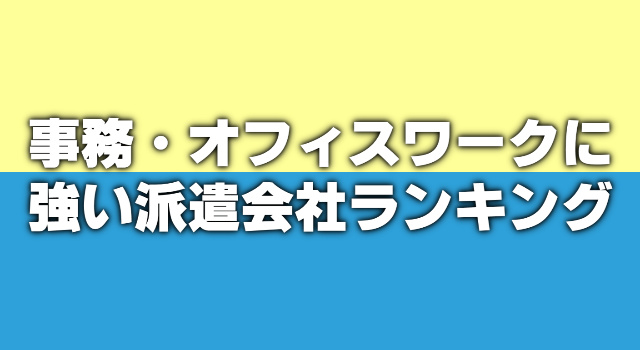

産休、育休という言葉は知っているし、派遣社員でも取得できるらしいという話は聞くけれど、果たして派遣で働く私も産休や育休が取得できるのか?
『インターネットで調べてみてもいまいち確信が持てない』
こういう方はすごく多いです。
妊娠中に、『育休中や産休中は、派遣の場合は収入はどうなるのか?』と疑問を持たれる人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、派遣社員の産休や育休制度に焦点を当て、取得できるのか?という基礎的なことから、取得するための条件、注意すべきポイント、その期間に受け取れる手当についてご説明していきます。
お子さんを出産する前に産休・育休制度についてしっかり学び、仕事や収入についての不安は全部なくしてしまいましょう。
目次
平成17年4月「育児・介護休業法改正」によって、一定の条件を満たした派遣社員も育休・産休を取得できるようになりました。
しかし、この知識はまだ広がっていないところも多く、「育休・産休は正社員だけ」と思っている企業も多いのが現実です。
ですが、法律上では労働者に認められた権利なので、そこで怯んでしまう必要はありません。
正社員や派遣社員などの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たしていれば産休・育休を取得する権利があるのです。
しかし、『一定の条件を満たしていれば』というところがポイントです。
どんな条件を満たす必要があるのか?産休や育休について個別に見ていきましょう。
産休は正式には「産前産後休業」といい、労働基準法第65条に定められたもので、それぞれ下記の通り休業の期間が決まっています。
派遣社員が産休を取得するための条件は『産休に入る時点で働いている』こと。たったこれだけです。
ちょっと拍子抜けしてしまいそうですが、働いている女性が出産するのための制度ですから、働いていればだれでも取得できる、というのは当然といえば当然ですね。
産前休業:
産前休業とは、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できる期間のこと。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
産後休業:
産後休暇とは、出産の翌日から8週間の就業不可期間(産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業可)のこと。
出産の翌日から8週間は強制的に休業となります。ただし医師の許可があれば産後6週間たてば就業できます。
産前休業は請求した人が取得するのに対し、産後休業はそもそも働くことができないという違いがあります。
産休を取得する条件はお分かり頂けたと思います。
しかし、産休を取得できれば手当も自動的についてくる、というわけではないので、ここは注意が必要です。
手当を受給するために必要な条件が手当ごとに少しずつ違うので、しっかり確認しておきましょう。
産まれる子ども1人当たり『42万円程度』が加入している健康保険から支給されます。
出産育児一時金を受けとるのに必要な条件2つ
1. 健康保険に加入していること
健康保険、国民健康保険どちらでも受け取れます。また、配偶者の扶養に入っている場合でも受給可能です。
2. 妊娠4ヵ月以降の出産であること
出産手当金は、出産育児一時金と同様に、加入している健康保険から支給されます。
出産予定日の42日前から、実際の出産後56日目までの期間、仕事を休んで給料が支払われなかった日数に対して手当が支給されます。
出産手当金を受給するための条件2つ
1. 自分自身が健康保険に加入していること
国民健康保険に加入している場合や、配偶者の扶養の場合は対象外となります。
2. 妊娠4ヵ月以降の出産であること
この計算式で手当の額が計算できますが、ちょっと堅苦しいですね。
大体の目安を知りたいだけなら、最近のお給料の月額を「30」で割って、その金額に2/3をかけた金額を1日分として計算してみるとよいかもしれません。
残業が多かったりして、他の月よりもお給料が高かった月で計算すると、実際に受け取る金額よりも大分高くなってしまうので気を付けてくださいね
産休を取得した場合、その期間中の社会保険料の支払いが免除されます。
こちらは産休に伴って免除されるものですので特別な条件はありません。
ですが、手続きがきちんとなされているか産休取得時に派遣元に確認するのがおすすめです。
育休とは育児・介護休業法で定められた「育児休業」のことで、男女の労働者が取得できます。
1歳未満の子どもがいる人は、会社に申し出れば、その子どもが1歳になるまでの間、希望する期間を休業できるという制度です。
2017年10月からは、認可保育園に入れなかったり、配偶者のけがや病気などが原因で子育てが難しくなったりした場合には『最長2年まで延長』が可能になりました。
派遣社員の育休取得の条件2つ
1. 育休取得の時点で過去1年以上継続して同じ派遣元で雇⽤されていること
派遣先が変わっていても、同じ派遣元でのお仕事を1年以上継続していれば問題ありません。
2. 子どもが1歳6か月になるまでの間に労働契約期間が満了することが明らかでないこと
「労働契約期間が満了することが明らかでない」というのは、『契約が切れることが確実ではない』ということです。
ご自分の契約書に、「契約更新がいつまで」「契約更新は何回まで」という表現がないか確認してみましょう。
そのような表現がなければ、『労働契約期間が満了することが明らかでない』ということになります。
気を付けなければならないのは、
といった、別の法律で制限されている契約期限です。
この期限が育休をとろうとする時期に重ならないか、早めに確認しておきましょう。
【育児休業給付金】
育児休業給付金とは、雇用保険から支給される手当で、期間によって支給額が変わります。
それほど難しい条件ではありませんね。
3つめの条件は、正社員で働いていて休業期間中でも会社から手当の支給がある場合などに関わってきます。
育休をとる派遣社員の方で育休中に就業する可能性はほぼないでしょうから4の条件についても問題なくクリアできそうです。
支給額について
育児休業開始~180日まで:『休業開始時賃金日額×支給日数×67%』
育児休業開始181日目以降:『休業開始時賃金日額×支給日数×50%』
【社会保険料の免除】
産休の期間同様、育休期間中の社会保険料の支払いも免除されます。
現状は、まだ産休・育休の文化や風習が構築されていない企業も多々あるというのが実情です。
また、産休や育休を取得できたとしても、復帰後の周りからの対応が心配な人も多数います。
派遣の場合は派遣先を変えれば問題ありませんが、正社員の場合は復帰後に自分の居場所がなく、口では言わないけど「辞めてくれ!」という状態だったという声もあがってきています。
短期の契約で働く派遣社員の立場としては、「産休を取得する直前まで契約の更新をしてもらうことなんて無理じゃないか」と心配になります。
ですが、平成17年に派遣社員でも産休・育休が取れるようになってから、取得のための条件が緩和されたり、より長い休みを取得できるようになったりと、法改正が進んできました。
それに伴い、派遣会社の制度もかなり整備されてきているので、産休や育休の取得も以前よりもかなり取得しやすい環境になってきているのは事実です。
特に大手は法律を遵守している企業ばかりなので、ちゃんとルールを守る派遣会社かどうか不安ならば、大手の派遣会社に登録することをおすすめします。
また、最近では『産休・育休を取得する間は、通常の派遣契約から、派遣企業と派遣社員との間の直接雇用契約に切り替える』という企業が多くなってきました。
その他にも、大手の派遣企業では、休業するスタッフの代わりに短期のスタッフを派遣することで、産休・育休が終了後はもとの職場へ復帰できるようにしているところもあります。
もし、出産の前に契約を打ち切られてしまったり、産休・育休取得の条件を満たせなかったりしても、あきらめないでください。
たとえば、出産育児一時金と出産手当金は、離職後も条件によっては受け取ることができます。
やむを得ず離職となってしまった場合でも、ご自分が手当てを受け取れるかどうか忘れずに確認するようにしてくださいね。
大手の派遣会社では、産休・育休制度を利用できることが公式ホームページ内で明言されているところもあります。
スタッフサービス
スタッフサービスグループでは、育児休業1ヶ月前までに当社を通して1年以上お仕事をされていて、産前6週間を含むご契約があり、育児休業終了後も引き続き当社での就業を希望されている方が、育児休業を取得できます。
引用URL:https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_047.html
パーソルテンプスタッフ
テンプスタッフはママが安心して仕事を続けていただけるよう、社会保険、有給休暇制度、健康診断、産休・育休制度などを完備。
一定の条件を満たすご就業中のスタッフの方が希望された場合には、産休・育休を取得できる制度がございます。
引用URL:https://www.tempstaff.co.jp/personal/women/pickup/
ここでは上記2社の紹介に留めますが、大手人材派遣会社であれば、法律順守が徹底されているので安心でしょう。
これから派遣登録をされる予定なら大手派遣会社に登録を。
既に派遣就業中の方は、ご自分の登録している派遣企業の制度がどうなっているか、確認してみてください。
残念ながら、産休・育休を申請して契約を打ち切られるという可能性はゼロではありません。
契約打ち切りに関しては、あなたが所属している派遣会社によるところが非常に大きいです。
もしあまり理解がなさそうな派遣会社に登録してお仕事しているのであれば、『産休・育休を取得したい』とはっきり要求してみることをおすすめします。
また、「今から派遣会社に登録する」という方は、派遣登録してからお仕事を紹介してもらう前に、産休・育休取得への対応について確認しておくとよいでしょう。
産休・育休の取得のための制度があるかどうかだけでなく、派遣会社の育休や産休制度への姿勢(ぜひとりましょう!と応援してくれるのかどうか)までチェックしてみることをおすすめします。
産休・育休の取得には申請の期限がありますので、事前に計画をたてて余裕を持って手続きを終えたいですね。
基本的な申請の流れを書いていきます。
期限や申請方法など、派遣企業ごとにルールがありますので、実際に申請する際はご自分の契約している派遣企業に必ず確認をとるようにしてください。
まずは派遣元に連絡して、産休・育休を取得するための準備をはじめましょう。
条件、必要な書類、手続き方法などをしっかりと確認します。
産休は「出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)」から取得できます。
その1ヵ月前くらい前、つまり出産予定日の2ヵ月半前くらいまでには申請を済ませましょう。
産休と同時に申請するのであれば期限を心配する必要はありません。
ですが、育児休業の申請の期限は、法律では育休開始予定日の1ヵ月前と決まっていますのでご注意ください。
申請書は派遣元から取得できます。
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金それぞれに個別の申請書の準備が必要です。
申請書の取得方法は派遣元に確認しましょう。
種類がたくさんありますので、申請漏れがないようチェックしてください。
慣れない手続きばかりですので、面倒に感じてしまうかもしれません。
ですが、期限が過ぎてしまって給付金が受け取れない!ということになっては大変です。
派遣元の担当者にも助けてもらいながら手続きをすすめていきましょう。
ただし、「派遣元の担当者に頼りきり」というのも考えものです。
担当者が産休・育休制度や手当てについてすべて理解しているという保証はありません。
厚生労働省のサイトのパンフレットなどを参考に、必要な手続きがもれていないか自分でも確認するようにしましょう。
出産は女性にとって大切なイベントです。
仕事への不安は早めに片づけて、新しい家族をゆったりとした気持ちで迎えてあげたいですね。
そのためにも、子どもが生まれるあなたのために準備されているこの制度を最大限活用しましょう。
条件を調べたり、慣れない手続きをしたりと準備は大変ですが、きっとがんばってよかった!と思えますよ。